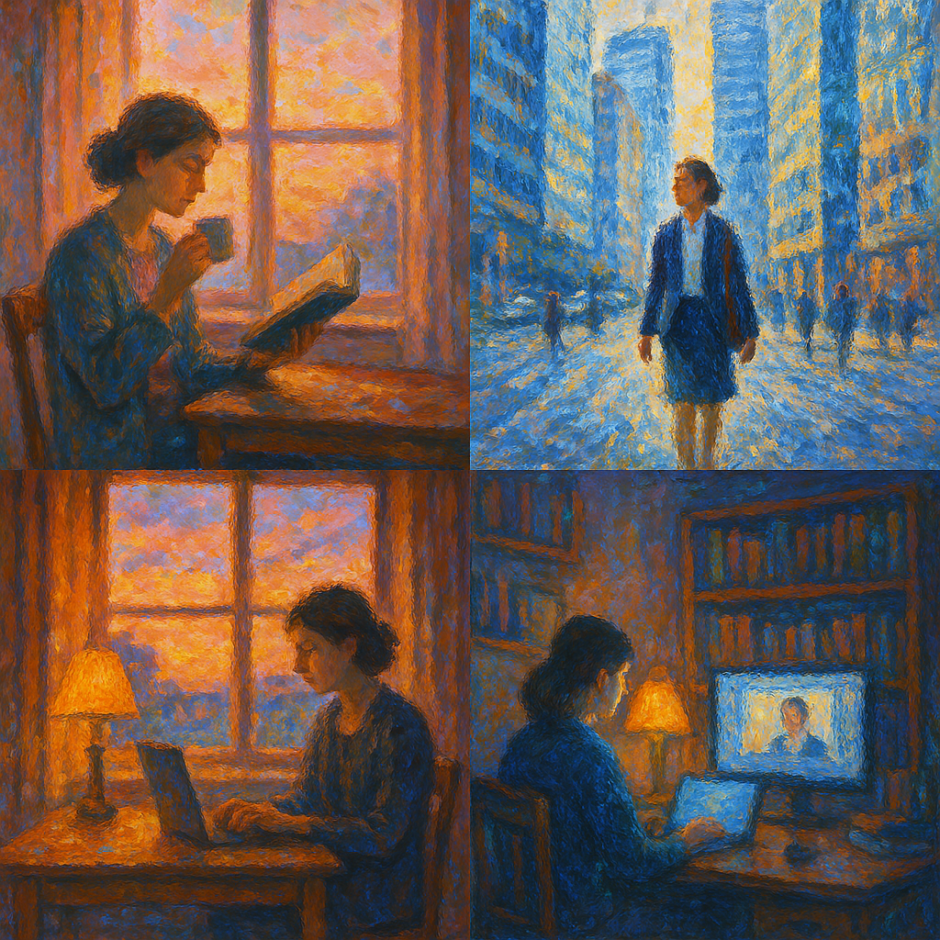【社会人大学院生の実態とは?】研究と仕事を両立する日々
社会人が大学院に通う理由はさまざまですが、主な目的は「キャリアアップ」「転職への準備」「研究への強い探究心」の3つに分けられます。
私の場合は、「残りの人生で研究に真剣に向き合いたい」という思いから、大学院への進学を決めました。単に知識を得るのではなく、問いを立てて深く掘り下げる思考力と、それを形にする実践力を身につけたかったのです。
現在は、週3日だけ非常勤で働きながら、大学院での学びを中心に生活を組み立てています。一見、時間に余裕がありそうに見えますが、授業・課題・研究とやることは山積みで、日々の時間配分は非常にシビアです。
社会人大学院生活で最も難しいのは「時間管理」です。授業を理解するための予習・復習、そして研究の計画や資料集めなど、自分で考えながら動く時間が圧倒的に多くなります。時間を有効に使わなければ、あっという間にタスクに追われてしまいます。
【平日のリアルなスケジュール】通勤・仕事・学びをどう回す?
社会人大学院生にとって、平日の時間の使い方がカギになります。忙しい中でも、自分なりにルーティンを整えることで、仕事と学業をバランス良くこなせるようになります。
まず朝は、通勤時間を「勉強タイム」に変換しています。私は通勤電車の中でKindleを使い、授業に必要な基礎知識をコツコツとインプット。朝の集中力が高い時間帯を活かすことで、その後の一日がスムーズになります。
仕事中は、「大学院の課題が気になる…」と思うこともありますが、気持ちを切り替えて目の前の業務に全力集中。成果を出すためのスキル習得や課題解決に取り組み、仕事は極力家に持ち帰らないようにしています。これが結果的に、学業とのメリハリにもつながっています。
夜の時間は、授業、課題、自己学習の時間です。「自分で選んで通っている」という意識が強い分、学びに対するモチベーションも自然と高まり、意外と集中できます。
【週末の過ごし方とリフレッシュ術】メリハリをつけて無理なく継続!
社会人大学院生にとって、週末は学びのゴールデンタイム。平日にこなせなかった課題や、興味のある論文の調査、さらには学会発表の準備など、集中して取り組める貴重な時間です。
私自身も、週末にはしっかり机に向かって学びを進めていますが、それと同じくらい心身のリフレッシュも大切にしています。大学院に通い始めてから運動の時間は減ってしまいましたが、通勤時の自転車や週2回のジムで、最低限の健康管理を意識しています。
また、継続のカギは「無理をしないこと」「習慣化すること」です。週に一度、自分の行動を振り返り、「本当に必要だったか?」を見直すことで、時間の使い方を少しずつ最適化しています。
「やろうと思ったことは、ダラダラせずその時間で終わらせる」意識が、結果的にストレス軽減と成果の両立につながっています。