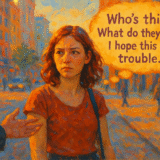上司からのサポートが「職場に馴染む」カギになるという研究の話
新しい職場にスムーズに馴染むためには、上司からのサポートが極めて重要です。
研究によると、中小企業で働く中途採用者において、上司の支援が組織理解を深め、職場への愛着を高めることが確認されています。
たとえば、仕事の進め方を丁寧に教えてくれたり、会社のルールや文化を明確に伝えてくれる上司がいると、不安やストレスが軽減されやすくなります。また、自分の意見や考えをしっかり受け止めてくれる上司がいるだけで、「ここで働いていていいんだ」という安心感が生まれ、組織への一体感も増します。
ただし、上司のサポートをただ待つのではなく、自分からも積極的に関わる姿勢が大切です。
・疑問があればすぐに聞く
・報連相をしっかり行う
・自分の経験やスキルを簡潔に伝える
こうしたアクションを意識することで、上司との信頼関係が築かれ、職場での居場所づくりがスムーズに進んでいきます。
組織社会化戦術が「職場に馴染む力」を高めるという研究の話
新しい職場で早く馴染むためには、会社側がどのように迎え入れてくれるかも大きなポイントになります。
研究では、中途採用者に対する「組織社会化戦術(=新入社員を組織に馴染ませるための取り組み)」が、職場への適応を後押しすることが明らかになっています。
特に注目されているのが、入社者の過去の経験や知見を尊重し、それを活かせる環境づくりです。これにより、本人のモチベーションが高まり、結果的に離職意図の低下やワーク・エンゲージメント(仕事への熱意と集中)の向上につながるのです。
若手社員や中途入社の人にとって、自分のキャリアやスキルを新しい環境でどう活かすかは大きな課題。
そんなときは、以下のような工夫が効果的です。
前職で得たノウハウを言語化して共有する
得意分野に関して自ら提案する
新しい業務と過去の経験をつなげて説明する
「受け身」ではなく、「自分の強みを活かしながら貢献する」スタンスが、職場での居場所づくりを加速してくれます。
リアリティ・ショックと人間関係が「職場適応」を左右するという研究の話
新しい職場に入ったとき、多くの人が直面するのが「リアリティ・ショック」です。
これは、入社前に抱いていた期待と、実際に働き始めてから感じる現実とのギャップから生じるショック状態を指します。研究によれば、このリアリティ・ショックは、組織へのコミットメントや離職意思に大きな影響を与えるとされています。
たとえば、「もっと自由な職場だと思っていたのに実際は縦社会だった」「仕事の裁量があると聞いていたのに、実際はマニュアル通り」など、理想とのズレに戸惑うケースは少なくありません。
このギャップを乗り越えるには、「事実を受け止め、どう前向きに適応していくか」というマインドセットの切り替えが重要です。そして、リアリティ・ショックを和らげるもう一つの大事な要素が、同僚との関係構築です。
信頼できる同僚ができることで、「相談できる」「愚痴が言える」「共感してもらえる」といった心理的な安心感が生まれ、職場に馴染みやすくなります。
以下のような行動を意識すると、自然に距離を縮められます。
朝の挨拶を丁寧にする
ランチや休憩時間に雑談する
仕事を手伝ってもらったら感謝を言葉にする
こうした小さな積み重ねが、「人間関係のストレスがない職場」という大きな安心感につながり、長く働ける環境づくりに直結します。
田中秀樹(2021)『中小企業における中途採用者の組織適応及び働きがい・定着意識向上に関する研究』、日本労働研究雑誌 特別号(No.727)、独立行政法人 労働政策研究・研修機構。
→ 中途採用者の適応において、上司からの支援が組織理解と愛着を促進することを実証。
塚原麻紀子・大場章史・吹田一人 他(2020)『中途採用者に対する組織社会化戦術と組織適応』、大阪大学経済学 第69巻第4号、pp.1-17。
→ 中途採用者における「経験や知見の尊重」が、ワーク・エンゲージメントの向上と離職意図の低下に寄与することを示した研究。
尾形真実哉(2012)『リアリティ・ショックが若年就業者の組織適応に与える影響の実証研究 ──若年ホワイトカラーと若年看護師の比較分析──』、組織科学 第45巻第3号、pp.49-66。
→ 入社前の期待と現実のギャップ(リアリティ・ショック)が、若年層の組織コミットメントや離職意思に大きな影響を与えることを明らかにした。